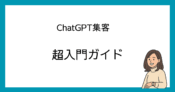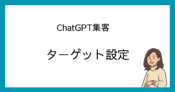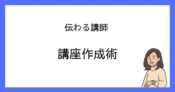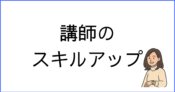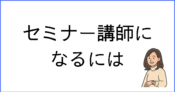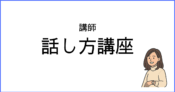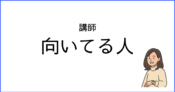講師業✖ChatGPT活用ガイド|初心者でもできるレッスン準備・資料作成の時短術
講師業をしていると、スライドやレッスン構成の準備に思った以上の時間を取られませんか?
一度構成を作ったはずなのに「やっぱりこっちの方がいいかも」「この順番で伝わるかな」と、見直しに追われる。スライドに至っては、「どの図がいいか」「どこまで説明すべきか」と悩み、気づけば1日が終わることも…。
実際、私も長年マーケティング講座の講師をしていますが、「構成を決める→悩む→作る→また悩む」の繰り返しで、思考と時間が消耗していました。
そんな私が、ChatGPTを導入してから、講師業の準備が一変しました。
構成の壁打ち、スライド設計、受講者ごとのカスタマイズ…「手間」と「迷い」の多くがAIに委ねられるようになったのです。
とはいえ、AIに任せきりにするのではなく、「講師として、人に届ける本質」は自分で持っておきたい。
本記事では、講師業におけるChatGPT活用のリアルな変化と、「AIに振り回されない自然体の使い方」について、私自身の体験を交えながらお伝えします。
ChatGPTで変わる!講師業の「5つの進化」
実際に私がChatGPTを使って変化した講師業の現場を踏まえながら、
どんなふうにレッスンの準備や内容が変化したのかを紹介していきます。
1. 講座構成に“悩む時間ゼロ”
以前は、講座の骨組みを考えるのに1日かけることもありました。
「順番はこれでいいのか?」「内容が偏ってないか?」「もっといい構成があるのでは?」と、答えのない迷路をぐるぐると彷徨うような日々。
でも今は、ChatGPTにこう聞くだけ。
「〇〇な人向けに、90分の講座をしたいです。自然体マーケティングをベースに、行動変容を促すような構成にしてもらえますか?」
たったこれだけで、「構成案+各セクションの要点+必要なスライドの枚数」が出てきます。
もちろん、全部そのまま使うわけではありません。
“あくまで壁打ち”としての活用です。「こうじゃない」「そうそう、こういう流れがしたかった」という自分の言語化・思考整理にもなっています。
2. スライドづくりが「ゼロからの創造」ではなく「整え作業」に
講師業で意外と時間がかかるのが、スライド作成。
以前は、
- デザイン迷子
- 文字詰めすぎ問題
- 伝わらないグラフ
- 図解が思いつかない
こんなことで1週間スライドとにらめっこしてたことも…。
でも今は、ChatGPTに以下のように伝えます。
「この講座構成に合うスライドのタイトルと流れを10枚分考えて」
「もっと視覚的にわかる構成にできないかな?」
「この講座のメインメッセージを1枚の図にして」
すると、「見せ方の原案」が一瞬で出てくる。
私自身は、それを自分のトーンで整えればよいだけです。
3. 受講者ごとの“最適化”が自然にできるように
事前アンケートで「今回は初心者が多いな」とわかれば、ChatGPTにこう聞きます。
「この内容を初心者向けにアレンジしてください」
「事例を身近な例(家事、日常、SNS投稿)に変えて」
「使う言葉を優しくして」
これまでならカスタマイズに時間がかかったけれど、今では言い換え・アレンジ提案も3分で完了。
“相手に合わせる配慮”が、ストレスなくできるようになりました。
4. 自分の内面を掘り起こす壁打ち相手に
講師は「教える」ことには慣れていても、「自分自身を語る」ことが苦手な人も多いです(私もそうでした)。
でも、自分の経験やストーリーを言語化して初めて「この人に教わりたい」が生まれる。
そのためにChatGPTをコーチング相手として使うようになりました。
たとえば、
- 「私の強みって何だろう?」
- 「このエピソードからどんな価値観が見える?」
- 「なぜ私はこの講座をやっているのか?」
こんな問いを投げると、ChatGPTは自分では思いつかなかった切り口で返してくれます。
5. 音声入力で“自然体”をキープ
喋るのは得意でも、文章にするとガチガチに硬くなってしまうタイプの人もいらっしゃいますよね?
そんな方は音声入力が絶対にオススメです。
私はChatGPTとのやりとりに音声入力を使っています。言葉で話すと、自分の中の“本音”が出やすく、体験談も感情も乗ったまま言語化できます。
「書こうと思うと止まる」人は音声で効率化していきましょう。
このように、ChatGPTを“自分の分身”や“サブ講師”のように使うことで、「本来やりたかった“生徒と向き合う時間”」にリソースを割けるようになりました。
講師業✖ChatGPT活用の注意点|“AI疲れ”にならないために
いくら便利でも、ChatGPTの使い方を間違えると、「使えば使うほど疲れる」「思ったほど時短にならない」という落とし穴にハマります。
ここでは、私自身の実体験も交えながら、講師業で使うときに気をつけたいポイントをお伝えします。
1. 最初は「逆に時間がかかる」ことを覚悟しておく
正直、最初はこう思ってました。
「ChatGPT使えば一瞬でスライドできるんじゃ?」
「構成も5分で決まるって書いてあったし」
でも現実は、“慣れるまではそんなに早くならない”んですよね。
- 表現がしっくりこない
- 出てきた構成がなんか薄い
- 自分のスタイルに合ってない
というように、「結局直す時間」がかかります。
私も最初の頃は「やっぱ自分のチカラだけでやった方が早い…」と思ったくらいです。
でも、それは“慣れてないだけ”でした。
テンプレを作ったり、プロンプトの型を整えることで、だんだんスピードが上がっていきました。
2. “成果主義”に引っ張られすぎない
ChatGPTを使い始めた当初、「もっと成果を出さなきゃ」「スライドの完成度をもっと上げなきゃ」と、自分を追い詰める気持ちが強くなってしまった時期がありました。
でもそれって、本末転倒。
AIはあくまで補助ツール。
自分の評価や成果までAIに委ねてしまうと、どんどん疲弊します。
だから今はこう考えています。
「最初の叩き台を出してもらう相棒」
「本当にやりたいことに集中するための余白づくり」
それが、私の自然体な付き合い方です。
3. 「生徒のための時間」は手放さない
講師の仕事は、単に知識を教えるだけではありません。
「相手の行動を変える」ことが本質だと考えて仕事をしています。
構成やスライドはChatGPTに任せられても、「この受講者さんに、今、何を届けるべきか?」という部分は、絶対に自分の頭で考えるべきところ。
だから私は今でも、以下の時間は必ず確保しています。
- アンケートの読み込み
- 課題の振り返り
- 参加者の変化に気づく時間
これがあるからこそ、「この講師でよかった」と言ってもらえるし、講師という仕事が“ただの情報提供者”にならずにすんでいると感じています。
4. “ChatGPT疲れ”を感じたときは…
「もうChatGPT開きたくない…」
「なんか最近、うまく使えてない気がする」
そんな風に感じたら、無理して続けなくてOKです。
一度手放して、「本来の自分のやり方」でやってみると、「やっぱりこの部分はGPTに任せた方がいいな」と、必要な部分が見えてきます。
※この話題に関連する記事:
👉 ChatGPT疲れ|成果主義からの解放と“自然体”のすすめ
まとめ|ChatGPTは講師業の“右腕”。でも軸は自分に
ChatGPTは、講座の構成づくりやスライド作成、個別対応のカスタマイズまでできる、非常に強力な相棒です。
- 講座のたたき台を最速で作れる
- スライドや台本の精度が上がる
- 受講者に合わせた対応がしやすくなる
- 自分の考えを言語化する壁打ち役になる
- 音声入力と組み合わせて作業スピードが上がる
これらの機能を使いこなせば、時間とエネルギーを節約しながら、講師として本当に大切な部分——受講者の変化に寄り添うこと、成果を出してもらうこと——に集中できます。
一方で、最初から完璧を求めすぎると「ChatGPT疲れ」にもつながります。
AIは魔法の道具ではなく、習熟してこそ本領を発揮するツールです。
講師という仕事は、単に知識を伝える役割ではありません。
受講者の“変化”を設計し、行動を促すファシリテーターでもあります。
だからこそ、ChatGPTの力を借りながらも、最終的な判断や設計は“自分の頭”で行うことが信頼につながる道です。
AI時代の講師業に必要なのは、“使われる側”になるのではなく、“使いこなす側”になること。
そして、“自分らしさ”を失わずに教える姿勢を持ち続けることです。