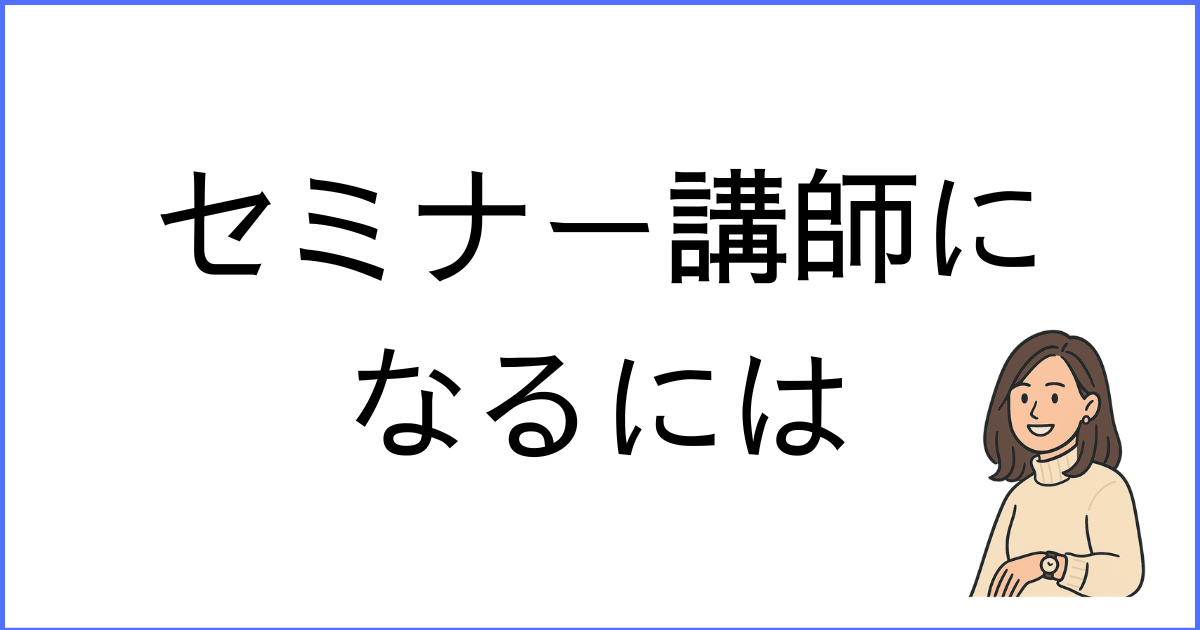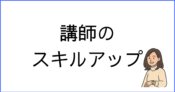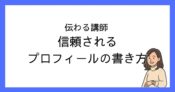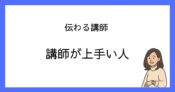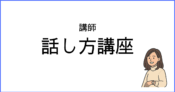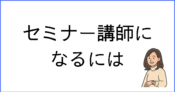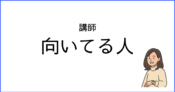500社で登壇して分かった「セミナー講師のなり方」|最初の仕事の取り方から講座設計まで
「セミナー講師になってみたいけれど、何から始めればいいんだろう?」
「未経験でも講師の仕事ってできるの?」
「どうすれば企業や行政から依頼が来るの?」
そんな疑問を持つ方に向けて、このガイドでは セミナー講師のなり方を最初の一歩から丁寧に解説します。
私は2018年から講師として活動し、行政・大手企業を含む500社以上の前で登壇してきました。
ですが、最初から自信があったわけではありません。
最初の講座は、コミュニティで無料開催した小さな機会でした。そこから経験を積み重ね、話し方・講座構成・プロフィールづくり・導線設計といった “講師の仕事の型” を磨きながら今の形をつくってきました。
今は生成AIが普及し、専門知識は誰でも手に入る時代です。
だからこそ、「相手に合わせて伝える力」 を持つ講師の価値はむしろ高まっています。
同じ内容でも「伝わる講師」と「伝わらない講師」の差が大きく出る時代でもあります。
本記事では、
- セミナー講師とは何をする仕事なのか
- どんな人が向いているのか
- 未経験が最初の仕事を取る方法
- 講座構成・話し方の基本
- そして収入をつくる道筋
これらを、あなたが 今日から動けるレベル でまとめました。
講師を目指すあなたの「最初の一歩」が、ここから始まります。
セミナー講師の仕事は「専門知識を届ける」以上の価値がある
セミナー講師という仕事は、単に“知識を説明する人”ではありません。
AIがどれだけ進化しても、むしろ AIが当たり前になった今だからこそ、講師にしかできない役割がはっきりしています。
今は、ChatGPTを使えば専門的な内容も数秒でまとめられます。
情報そのものは、無料でも、AIでも、どこからでも手に入る時代。
では、それでもなぜ企業・行政・個人は「講師」を必要とするのでしょうか?
理由はとてもシンプルで、“聞き手に合わせて必要な情報だけを選び、理解しやすい形に翻訳して届ける力”は、AI単体では代替できないからです。
セミナー講師の価値は、知識量ではなく “伝わるように設計する力” にあります。
- 聞き手のレベルに合わせて順番を組み替える
- 例え話でイメージを補う
- 情報を必要な分だけに圧縮する
- 聞き手が動きたくなる言葉を選ぶ
こうした「伝え方の設計」は、目の前の人を理解し、人に寄り添う力があって初めて成立します。
実際、私が行政や企業向けに500社以上で講座を行ってきて感じるのは、
評価されるポイントは常に “分かりやすさ” と “届け方の丁寧さ” だということ。
どれだけ専門性が高くても、構造がバラバラだったり、話が難しすぎたりすると、理解は広がりません。
逆に、内容そのものはシンプルでも “流れが良い講座” は一気に伝わる。
この「伝わる設計」が講師の価値そのものです。
このように、セミナー講師は“知識を話す人”から、
“相手の変化をつくるファシリテーター”という役割へと進化しています。
AI時代だからこそ、講師という仕事は確かな価値を持ち続けています。
セミナー講師に向いている人・向いていない人
セミナー講師に向いているかどうかは、話し方のうまさやカリスマ性とは関係ありません。
500社以上の前で講座をしてきた実感として、講師の“適性”はもっと日常的で、小さな姿勢の積み重ねにあります。
まず、向いている人の共通点は 「相手を見て話せるかどうか」 に尽きます。
向いている人の特徴
- 相手視点で話せる人
自分が言いたいことより、相手が“受け取りやすい言葉”を選べるタイプ。 - 経験を言語化できる人
成功も失敗も、気づきを言葉にできると講座に深みが出る。 - 観察力がある人
うなずき・沈黙・表情から、受講者の理解度を察知できる。 - 改善できる人
終わった後に「次はこうしてみよう」と考えられる。 - 等身大で向き合える人
背伸びしない自然体の講師は、受講者の安心感が段違い。
これらはすべて“特別な才能”ではなく、実践を重ねるほど自然と身につく力です。
一方で、「向いていない」と感じる傾向は、どれも直せるクセなので安心してください。
向いていない人の特徴
- 完璧に話そうとする人
緊張が伝わり、受講者まで固くなる。 - 情報を詰め込めば価値が出ると思う人
“詰め込み型講師”は伝わりにくく、印象に残りにくい。 - 自分の話に酔ってしまう人
相手が置いていかれ、独りよがりになる。 - 弱みや失敗を隠す人
等身大の話に共感が生まれ、信頼につながるため「隠す」は逆効果。
ただ、これらはすべて“意識を変えるだけで改善する”ものです。
講師の適性は固定ではなく、伸ばせるスキルの集合体だと感じています。
最後に、500社で登壇してきた中で分かったのは、
伝わる講師には必ず「構造化する力」があるということ。
伝わる講師の共通点
- 話の「順番」を意識している
- 必要な情報だけに絞って伝える
- 例え話でイメージを補う
- 受講者の反応を見ながらペースを調整する
- “自分の話”ではなく“相手の理解”を中心にしている
特に「順番の良さ(構造化)」は、講師の質を左右する決定的ポイントです。
より詳しい内容は、別記事で深く解説しています。
セミナー講師になるための3ステップ
セミナー講師として活動を始めるために、特別な資格や“すごい経歴”は必要ありません。
必要なのは、相手に届けたい想い と 伝わる形に整える準備 です。
500社以上の現場で登壇し、講師育成にも携わる中で感じるのは、
“講師の最初の一歩” には共通の流れがあるということ。
この章では、未経験からでも着実に講師として動き出せる 3つのステップ をまとめます。
ステップ①:自分の専門領域と「伝えたい一言」を言語化する
講師として活動する前に、まず必要なのは 自分の専門性と言語化された軸 を持つこと。
多くの人がいきなり「講座を作ろう」として迷子になりますが、
最初にやるべきは 台本より前の設計 です。
- 自分はどの領域なら教えられるのか
- どんな人の役に立ちたいのか
- その人に最初に伝えたい“たった一言”は何か
この一言が決まると、講座のテーマも構成もぶれなくなります。
逆にこれが曖昧だと、情報が散らかった“何を伝えたいのか分からない講座”になりがち。
誰しも最初は、「伝えたいことは多いのに、結局まとまらない」という壁にぶつかったはず。
でも、“届けたい一言” を明確にした瞬間、講座設計のスピードが一気に上がります。
講師の軸はここから生まれます。
ステップ②:1分自己紹介と講師プロフィールを整える
講師の仕事は あなた自身が選ばれる仕事。
だからこそ、講座内容より先に プロフィールの整備 が必要です。
ここで作るべきは2つ。
- 1分自己紹介(対面・オンライン両方で使える)
- 講師プロフィール(ブログ・SNS・依頼ページに掲載する用)
“1分自己紹介” は、講座の冒頭で参加者との距離を縮めるための大切なパーツです。
- どんな経験があるのか
- なぜこのテーマを教えるのか
- 今日の講座で何を持ち帰ってほしいのか
これらを簡潔に伝えられるだけで、参加者の理解度と安心感は大きく変わります。
プロフィールの基本については、別記事でも書いております。
わたし自身、ここを整えたことで、大手企業からの依頼につながった実例があります。
講師として活動するなら、必ず押さえておきたい重要ステップです。
ステップ③:小さな場で話して経験を積む
講師のスキルは“実戦”で一気に伸びます。
最初は、
- 無料の小さな講座
- 友人・知人との勉強会
- コミュニティ内でのミニセミナー
こうした リスクの低い場で練習する のが最も効果的。
わたし自身も最初のセミナーは、所属していたコミュニティで無料開催しました。
参加者の反応や質問から講座内容を磨き、積み重ねてきました。
最初から完璧を目指す必要はありません。
小さな場で話してみると、必ず “次に改善すべきポイント” が見えてきます。
- どの部分で受講者の理解が止まったのか
- どの例え話が刺さったのか
- どのテンポが心地よかったのか
これらは、実際に話してみないと絶対に分からないもの。
講師の成長スピードは、「準備」ではなく「実践回数」 で決まります。
最初の仕事の取り方|未経験でも依頼につながる方法
「講師の仕事は、どうやって最初の1件が来るの?」
これは多くの人が抱える最大の疑問です。
最初の仕事は“資格”や“大きな実績”からではなく、
小さな発信・小さな接点・小さな実践 から生まれます。
500社以上の前で登壇するようになった今でも、
最初の依頼が来たプロセスを振り返ると、共通点はとてもシンプルでした。
SNSやブログでの“日常的な発信”から依頼が来る
意外かもしれませんが、最初の依頼は 「講師向けの発信」をしていなくても来ます。
私も最初の講師依頼は、
- SNSでのマーケティング発信
- ブログでのノウハウ記事
から「話してみませんか?」と声をかけられたのが始まりでした。
人は、“専門性だけ”ではなく
「この人の視点は分かりやすい」
「言語化の仕方が好き」
という感覚で依頼します。
ポイントは、専門性 × 発信の一貫性。
AIが台頭した今は、文章生成も動画生成も誰でもできますが、
「あなたの視点」だけはAIでは作れない。
この視点が講師としての価値につながります。
実績ゼロでも依頼が来るプロフィールの作り方
最初に整えるべきは、大げさな経歴ではなく “理由”と“軸”。
- なぜこのテーマを伝えているのか
- 過去にどんな経験をしてきたのか
- 誰のどんな悩みを解決したいのか
この3つが明確だと、実績の大きさより“納得できる人物像”が伝わります。
実際、あなたも最初の頃は
「講師としての実績」より「言語化のわかりやすさ」で依頼されましたよね。
仕事を獲得するためのプロフィールの詳しい書き方は別記事にまとめています。
行政・企業研修につながった“導線の実例”
私が行政・企業から依頼されるようになった経緯はとてもシンプルです。
- 自分の専門テーマで継続発信
- 講座やスライドが見られる
- 「この人は話が分かりやすい」と認知される
- 企業・行政側が検索またはSNSで発見
- 研修依頼につながる
どんな講師志望者にとっても現実に起こりえる流れです。
- 6回講座を100〜150社に向けて4年連続で実施
- そこから他の講座依頼が芋づる式に増えた
このようなことが起きてくるのでぜひ発信活動をしていきましょう。
小さな講座が“次の仕事”の起点になる
講師の仕事は、1回の講座から次の講座が生まれる仕事です。
- 分かりやすかった
- また聞きたい
- うちのチームでもやってほしい
- 別テーマもお願いできる?
この連鎖が起きると、依頼は自然に増えていきます。
だから最初は“大きな仕事”を狙う必要はありません。
わたし自身も、コミュニティでの無料講座からすべてが始まりました。
そこから企業講座、行政講座、講座販売へとつながっていきました。
講師のキャリアは、「小さな実績 × 丁寧な講座」の積み重ねで構築されます。
講座の作り方|受講者が動きたくなる構成の作り方
セミナー講師にとって、講座の良し悪しを決めるのは“専門知識の量”ではありません。
もっと大切なのは、受講者が理解し、納得し、行動したくなる構造になっているかどうかです。
私は講座づくりをサポートしてきた中で、そして自分自身が500社以上の現場で登壇してきた中で、
「伝わる講座」には必ず共通点があると感じています。
ここでは、どんなテーマでも応用できる 講座設計の基本構造 を紹介します。
結論 → 理由 → 例 → まとめ の「鉄板構造」を押さえる
どんな講座でも、まず押さえておきたいのが 話す順番の型 です。
構造の良い講座は、聞き手が迷いません。
私がよく使っているのは、この4つの流れです。
- 結論(まず何が大事なのかを示す)
- 理由(なぜそれが必要なのか)
- 例(具体的な事例や体験談)
- まとめ(要点を整理し、行動につなげる)
この順番で話すだけで、受講者の理解度は大きく変わります。
内容が難しいテーマほど、構造の良さが“分かりやすさ”を支えてくれます。
行政講座の満足度が高かった理由も、専門知識そのものより 構造のわかりやすさ だったと感じています。
専門知識は“全部入れる”のではなく“必要な分だけに絞る”
講師初心者がつまずきやすいのが、情報を詰め込みすぎること。
「全部伝えないと価値がないのでは?」
と感じる気持ちはよく分かります。
でも実際は、
受講者が今日から動けるレベルに情報量を絞る方が、満足度が上がります。
ポイントは3つ。
- 受講者が“まずやるべき1つ”を明確にする
- 専門用語は使いすぎない
- 例え話でイメージを助ける
講座の価値は「情報量」ではなく、
“理解できた量” × “行動に移せる量” です。
例え話・ストーリーを使うと理解が進む
私が講師として強く実感しているのは、
人は“理解”より “納得” で動くということ。
そのために最も役立つのが、例え話やストーリーです。
- 自分の失敗談
- 過去の相談者の変化
- 日常のちょっとした気づき
こうした話は、専門理論よりもはるかに印象に残ります。
特にオンライン講座では、ストーリーが集中力の要になります。
ワークを入れると講座の満足度が跳ね上がる
“聞くだけの講座”より
“考える・書く・話す講座”は満足度が高くなります。
ワークを入れると…
- 理解が深まる
- 自分ごとに落とし込める
- 行動しやすくなる
というメリットがあります。
ワークは大きくなくて大丈夫です。
たとえば、
- 書き出し3分
- ペアワーク5分
- 1つ質問に答えてもらう
こうした“小さなワーク”が講座を動かします。
まとめ:講座づくりは「順番 × 絞る × 例 × ワーク」
講座は“全部を話す場”ではありません。
受講者が今日から動ける状態にする場です。
そのために必要なのは、
- 話す順番(構造)
- 情報の絞り込み
- 例え話・ストーリー
- 小さなワーク
この4つ。
講座設計は才能ではなく技術なので、誰でも磨いていけます。
セミナー講師の話し方|聞き手が「分かりやすい」と感じるポイント
講師の価値は“話し方”で大きく変わります。
とはいえ、必要なのはアナウンサーのような完璧な発声ではなく、
「相手に届く話し方」 です。
私はこれまで、行政・企業向けを含む500社以上の前で講座を行ってきましたが、
評価の内容はいつも専門知識ではなく、
- 話の順番が分かりやすい
- 声の温度感が心地よい
- テンポが良くて聞きやすい
- 例え話が理解しやすい
など、“届け方”に関するものがほとんどでした。
講師の話し方は、大きく3つの力の掛け合わせで決まります。
話し方①:話す「順番」が良いこと(講師型の構造)
話し方と言うと「声」をイメージしがちですが、
話の構造(順番) も大切です。
- 結論 → 理由 → 例 → まとめ
- 抽象 → 具体
- Before → After
この流れを意識するだけで、受講者の理解度は大きく変わります。
私が行政講座で高い評価をいただいてきた背景にも、
この“構造の一貫性”があります。
話し方②:声・表情・ペースは「構造を届けやすくする」ための要素
声を良くしようと無理に作り込む必要はありません。
講師に求められるのは 「温度感が伝わる声」 です。
- ここはゆっくり大事に話す
- ここはテンポよく進める
- 感情を1割だけ声に乗せる
- 表情を少し柔らかくする
こうした小さなコントロールが、オンラインでもリアルでも“聞きやすさ”を支えます。
特にオンライン講座では、表情や間が伝わりづらくなるため、
ペース(緩急) の重要度が上がります。
話し方③:一方通行ではなく「対話するように話す」
伝わる講師は、話が一方通行ではありません。
- 「…ですよね?」と問いかける
- 受講者の反応を拾う
- うなずきを待つ“間”をつくる
- カメラ目線で話す(オンライン)
これだけで“参加している感覚”が生まれ、理解度がぐっと上がります。
行政講座で反応が薄い場面があったときも、
私はこの「対話の姿勢」を崩さず話し切ることを意識しました。
講座後に熱い感想が届くことが多く、
反応が薄い=伝わっていない、ではないと実感しています。
さらに詳しい講師の話し方については別の記事でも解説しています。
セミナー講師として収入をつくる方法
セミナー講師の収入源は、実はひとつではありません。
単発の講座だけで生活している人は少なく、多くの講師は 複数の収益ラインを組み合わせて安定化 させています。
私自身も、企業研修・行政講座・オンライン講座・教材販売など、複数の柱を組み合わせることで「教える仕事」を継続してきました。
ここでは、未経験からでも作りやすい収入ルートを、わかりやすく整理します。
① 単発のセミナー登壇(もっとも始めやすい)
最初に収入になるのは、単発のセミナー依頼です。
1回あたりの報酬はテーマや主催者により異なりますが、だいたい下記が目安。
- 個人・小規模団体:5,000〜30,000円
- 企業:30,000〜300,000円
- 行政・商工会議所:50,000〜150,000円
- 大型研修会社:100,000円〜
私の場合、行政講座(6回セット)を4年連続で担当し、
100〜150社の前で話す機会が継続的な収益につながりました。
単発登壇は、実績づくりにも非常に有効です。
② 継続型の企業研修・内部研修
単発登壇の次に目指したいのが 継続研修 です。
企業は、
- 新人研修
- 営業研修
- デジタルリテラシー
- マーケティング研修
など、年間企画として講座を組むケースが多く、
ここに入れると安定収入の柱になります。
報酬の目安は
- 月1回×3ヶ月〜半年
- 1回あたり5〜15万円
というケースが多いです。
継続研修につながるのは、
「分かりやすい」×「丁寧」×「再現性がある」講師。
ここを強みにしていくと研修を依頼されやすくなっていきます。
③ オンライン講座・動画教材(スケールする収益)
講師の大きな武器になるのが 動画教材 と オンライン講座。
- 販売の自動化がしやすい
- 時間に縛られない
- 多くの人に届けられる
- 講師としての専門性が伝わる
私の場合、動画教材を販売しながら、企業から「この内容を研修でも扱いたい」と依頼が来た事例もあります。またUdemyというシステムを使い20,000名以上の方に届けています。
1本の動画教材が、
収益・集客・信頼のすべてを作る のは講師業ならではです。
④ 個別相談・コンサルティング
講座を聞いた人の中には、
- 自分の講座も作りたい
- 話し方を個別に見てほしい
- プロフィールを一緒に作ってほしい
という人が必ず出てきます。
講師業は “講座 → 個別相談” の導線相性が非常に良いのが特徴。
私もセミナーのあと個別相談で初成約に至った経験がありました。
ここは高単価な商品を提供しやすい場所でもあります。
⑤ 自主講座・コミュニティ運営
講師として軸が固まってきたら、
自分で講座を企画したり、コミュニティを運営するのも選択肢。
- 単発講座(5,000〜50,000円)
- 継続講座(30,000〜数十万円、数百万円など)
- コミュニティ(月額制)
これらは「自分が届けたい内容」を形にできるのが最大の魅力。
セミナー講師を目指す人が最初にやるべきこと
セミナー講師は、資格や大きな実績がなくても始められる仕事です。
でも、闇雲に動くよりも 最初の3つの準備 を押さえておくと、講師としての土台が一気に整います。
私自身も、この3つを抑えたことで講師活動がスムーズに進み、
行政・企業への登壇依頼にもつながる流れを作ることができました。
① 自分の「伝えたい一言」を決める
講座を作る前に、まずは 自分の軸をひと言で言語化 してみてください。
- どんな人の役に立ちたいのか
- 何を一番伝えたいのか
- どんな変化を起こしたいのか
この一言が決まると、講座テーマも話す内容もブレなくなります。
多くの人は「講座内容」から考え始めて迷いますが、
本当のスタート地点は “あなたが何を届けたいのか” です。
② 講師としての「1分自己紹介」を作る
講師の仕事は、あなた自身が“選ばれる”ところから始まります。
だからこそ、最初に整えるべきは 1分自己紹介。
- なぜこのテーマを話すのか
- どんな背景や経験があるのか
- 今日は何を持ち帰ってほしいのか
この3つが入っているだけで、講座の冒頭で一気に信頼感が生まれます。
私自身、1分自己紹介を整えたことで、
講座の入りがスムーズになり、参加者との距離が近くなるのを実感しました。
自己紹介テンプレはメルマガ特典として配布予定なので、
ここから登録して受け取ってください。
(講師or講師志望の方専用です。同業者や講師育成の立場の方は登録不可)
③ 小さな場で“まず話してみる”
講師のスキルは、準備より実践回数 で伸びます。
最初の場は大きくなくて大丈夫。
- 小規模コミュニティ
- SNSのライブ
- 無料のオンライン勉強会
- 少人数のミニ講座
こうした小さな実践のほうが、初めての講師にとっては最適な“練習の場”になります。
私も最初は、小さなコミュニティで無料講座をしました。
参加者の反応や質問に触れながら、伝え方を少しずつ改善していきました。
この小さな積み重ねが、企業・行政講座につながる土台になっています。
まとめ|セミナー講師は「伝えたい想い」から始まる仕事
セミナー講師は、特別な資格や派手な実績がないと始められない…
そんなイメージを持たれることが多い仕事です。
ですが実際は、
あなたの経験・視点・言語化した一言が、誰かの理解や行動につながる。
その力を形にするのが、セミナー講師という仕事です。
AIがどれだけ進化しても、“人に合わせて翻訳して届ける力”は代替されません。
講師はこれからの時代、むしろ価値が高まり続ける仕事だと感じています。
この記事で紹介した内容は、どれも今日から動けるものばかり。
- 伝えたい一言を決める
- 1分自己紹介を整える
- 小さな場で話してみる
- ブログやSNSで視点を発信する
この小さな積み重ねが、講師としてのキャリアをつくります。
さらに詳しく学びたい方は、こちらの記事もおすすめです。
また、講師として活動を始めたい方に向けて、
「講師の1分自己紹介テンプレ」 をメルマガ特典として配布しています。
講師の軸づくりが一気に楽になるので、ぜひ受け取ってください。
あなたの経験や言葉は、誰かの“行動のスイッチ”になれます。
セミナー講師は、それを丁寧に届ける仕事です。
小さな一歩から、一緒に積み上げていきましょう。