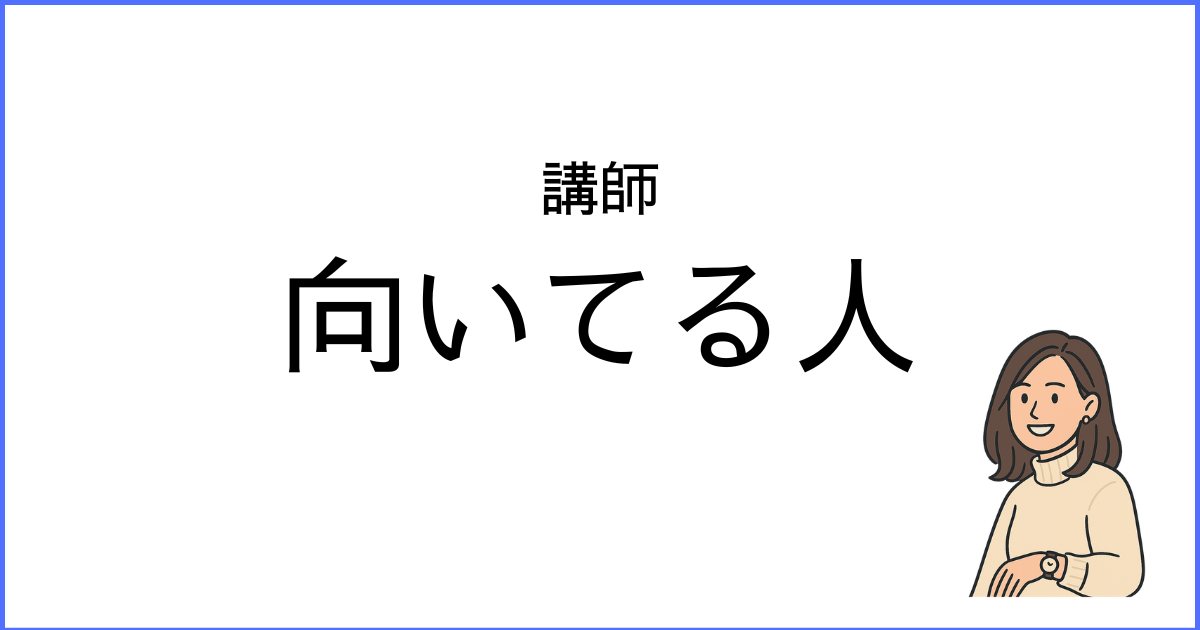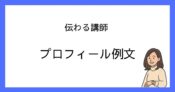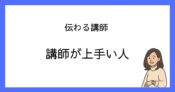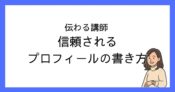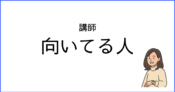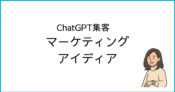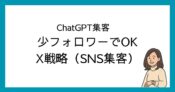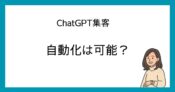講師に向いてる人・向いてない人|500社で話して分かった“伝わる人”の共通点
講師になりたいけど、
- 「私って講師に向いているのかな…?」
- 「話すのが得意じゃないと無理?」
- 「向いてない人の特徴ってある?」
こう感じたことはありませんか?
私は2019年から講師として活動し、これまで 中小企業〜大企業・行政まで500社以上 に登壇してきました。
そして、多くの受講者・講座主催者・講師志望の方と接する中で、
「講師に向いている/向いていない」の本質がはっきり見えてきました。
結論から言うと、
“話がうまいかどうか”は、講師に向いているかの基準ではありません。
むしろ、私が多くの現場で見てきたのは、
- 最初は話し下手だった人が、講師として愛されるようになる
- 逆に、話すのが得意な人ほど伝わらないことがある
という現象です。
この記事では、
500社に講座をして見えてきた「講師に向いている人・向いていない人」を、
実例や心理の視点も交えてお伝えします。
「向いてない」と感じていた人ほど、読むと希望が湧くかもしれません。
第1章:講師に向いている・向いていないは「話のうまさ」で決まらない
多くの人が「講師=話がうまい人」というイメージを持っています。
しかし、2018年から講師として登壇してきた経験から断言できます。
話がうまいかどうかは、講師の適性とはほぼ関係ありません。
むしろ、話が得意な人ほど「伝わる」より「うまく話す」に意識が向き、聞き手に届かないケースさえあります。
講師の仕事は、“自分が話すこと”ではなく“相手に届く状態をつくること”。ここを誤解していると、どれだけ言葉を並べても伝わりません。
以下では、私が実際の現場で感じてきた「うまさでは決まらない理由」を深掘りしていきます。
講師の価値は“話し方”ではなく“届け方”にある
講師業は「プレゼンの上手さ」を競う仕事ではありません。
大事なのは、
相手の頭と心に“届く形”に言葉を変換する力です。
同じ内容を話しても、
- ある講師の話はスッと入ってくる
- 別の講師の話は難しく感じる
という違いが生まれます。
この差を作っているのが、届け方の設計です。
たとえば、
- 専門用語を“生活の言葉”に訳す
- 話す順番を相手目線で組み立てる
- 「何を伝えるか」より「どう受け取られるか」を意識する
こうした“設計力”が講師の価値そのもの。
だからこそ、言語化や発信設計が得意な人は、話し方が苦手でも講師として活躍できます。
最初から話し上手な講師はほとんどいない理由
人から愛されている講師も、最初から話し上手だったわけではありません。
むしろ、
- 緊張しやすい
- 早口になってしまう
- 何を話せばいいか迷う
こうした状態からスタートしています。
理由はシンプルで、講師業は
「知識」ではなく「場数」で伸びる仕事だからです。
- 言葉の選び方
- 間の取り方
- 例え話の入れ方
- 聞き手の反応の読み取り方
これらは実際の講座で初めて分かるもの。
話す才能より、コツコツ改善できる姿勢が重要になります。
むしろ「最初は不安だった人」の方が伸びる
最初から話し慣れている人より、
「本当に伝わっているかな…?」と心配するタイプの方が伸びやすい。
なぜなら、不安を感じる人ほど、
- 相手の反応をよく見る
- 分かりにくいポイントを改善しようとする
- 一方的に話さず “寄り添い” を意識する
という姿勢が自然と身につくからです。
講師は“うまく話す人”ではなく、
“相手を大切にできる人”が選ばれる仕事なんです。
第2章:講師に向いている人の5つの特徴
講師に向いている人には、特別なカリスマ性や話術が必要だと思われがちです。
ですが、正直それらは必須のスキルではありません。
講師に向いている人の共通点は、「話す才能」ではなく「向き合う姿勢」にある
ということ。
ここでは「伝わる講師」になる人が持っている5つの特徴を紹介します。
① 「相手の理解」を基準に話せる人
講師として最も強い適性は、
“自分が言いたいこと”より“相手が受け取れる言葉”を選べる人。
たとえば、
- 難しい言葉を避ける
- 例え話や図解で補う
- 参加者のレベルに合わせて説明を変える
こうした配慮ができるだけで、講師としての価値は一気に上がります。
逆に、話がうまくても“相手が理解できないスピードや言葉”を使う人は講師向きではありません。
理解基準で話せる人は、どんなテーマも“伝わる形”に変換できる人。
これは講師の最大の武器です。
② 自分の経験を“言語化”できる人
講師は知識だけでなく、経験から生まれる言葉が強く響きます。
- なぜその方法を選んだのか
- どこでつまずいたのか
- どんな工夫で乗り越えたのか
こうした“プロセス”を言語化できる人は、受講者にリアルな価値を届けられます。
完璧である必要はありません。
むしろ、失敗談・迷い・気づきを言葉にできる人ほど信頼される。
私も講座で「話し方が変わった体験談」や「反応が薄い中でやりきった話」を語ると、反応が劇的に上がります。
③ 聞き手の反応を観察できる人
講師に向いている人は、
“相手の微細な反応”をキャッチできる人。
- 表情
- うなずき
- ふとした沈黙
- チャットの書き込み
- 質問の空気
こうした小さな変化から、
「ここが難しかったかな」「もっとゆっくり話そう」
と場を調整できます。
特にオンライン講座では、反応が薄くても読み取る力が必要。
相手の小さな変化もキャッチしていきましょう。
④ 学びながら改善できる人
講師に向いているのは、
“1回ごとに学び、1回ごとに改善できる人”。
講座は回数を重ねるほど、
- 伝える順番
- 例え話
- 間の取り方
- スライドの見せ方
- 声のテンポ
がどんどん整っていきます。
完璧主義より、
「次はここを変えてみよう」
と1ミリずつ改善できる人が圧倒的に伸びます。
実際、最初は話が得意でなくても、改善力のある講師は数ヶ月で別人レベルになります。
⑤ “自然体”で向き合える人
多くの人は「講師だからしっかりしなきゃ」と思い込みますが、
講師に向いているのはむしろ “自然体で話せる人”。
- 作り込んだキャラ
- 必要以上のテンション
- 完璧に見せようとする姿勢
こうした“演じている感じ”は聞き手にすぐ伝わります。
反対に、
- 誠実さ
- 安心感
- 等身大の温度
- ちょっとした失敗や本音
この“人間味”にこそ、信頼が宿るんです。
講座で“話し言葉”をあえて入れたり、本音の一言で空気をほぐしたり、自然体で向き合える人は、ずっと愛され続ける講師になれます。
第3章:講師に向いていない人の特徴
「自分は講師に向いていないのでは…?」
そう感じている人の大半は、才能ではなく“ちょっとしたクセ”が原因です。
私は500社に向けて講座をしてきましたし、
有料・無料を問わず他の人の講座に参加をしたこともあります。
たくさん参加してきた中で感じたことは、講師に向いていない人はいないということ。
ですが、ついやっていしまう改善ポイントはあります。
次の5つの特徴に仮に当てはまっているなら…
改善して、“伝わる講師”に近づいていきましょう。
① 完璧に話そうとしてしまう
完璧を求めるほど、人は不自然になります。
- 表情が固くなる
- 声の抑揚がなくなる
- ミスを恐れて言葉がぎこちなくなる
すると、聞き手のほうが緊張してしまい、空気が固まります。
講師に必要なのは完璧さではなく、
“人間らしさ”や“安心感”。
自然体のほうが、圧倒的に伝わりやすく信頼も得られます。
わたし自身も、最初は台本通りに話そうとしすぎていた時期がありました。
ですが、そこから“本音を少し混ぜる”ことで場の空気が一気に変わった経験をしています。
② 情報量を多くすれば価値が出ると思っている
これは講師初心者が必ず通る道。
「せっかく時間をもらっているから、全部届けたい!」
という気持ちは分かりますが、
情報が多い=価値が高い、ではありません。
むしろ、
- 理解する余白がなくなる
- ペースが速くなり聞き手が置いていかれる
- 結局なにが大事だったのか伝わらない
という“詰め込み型講師”になりがち。
講座は料理と同じで、
お腹いっぱいより“ちょうどいい満足感”のほうが記憶に残ります。
③ 自分の話に酔いやすい
話し慣れてくると陥りやすいのがこれ。
- うまく話せたことに意識が向く
- 自分のテンションだけが上がっていく
- 聞き手の理解レベルが見えなくなる
こうなると “伝える”ではなく“披露する”話し方 になってしまいます。
講師の役割は、
「自分の話」ではなく「相手の理解」を中心に置くこと。
どれだけ話が流暢でも、相手が理解していなければ意味がありません。
④ 失敗談や弱みを見せられない
これは意外と多い特徴です。
「講師は弱みを見せてはいけない」
と思う人ほど、信頼されにくい。
理由はシンプルで、
弱みは“距離を縮める最強の武器”だからです。
- 失敗した話
- うまくいかなかった時期の話
- そこから立て直した話
こうしたストーリーは、聞き手に安心感と共感を与えます。
わたしも講座で“初期の失敗談”を話すようになってから、反応が驚くほど変わりましたよ。
⑤ 聞き手の目線に立てない
講師として最も改善すべきポイントはここです。
自分の話したいことを中心に置くと、
- 一方通行になる
- 例え話がなくて難しく感じる
- 聞き手がついてこれているか分からない
という“伝わらない講座”になりがち。
でも、これはすぐに直せます。
- 「ここ難しくないですか?」と声をかける
- ペースを調整する
- 参加者の表情や反応を観察する
- 小さな質問を投げる
こうした“聞き手中心の姿勢”があるだけで、伝わる力が劇的に上がります。
第4章:500社に話して分かった「伝わる講師」の共通点
企業向けは500社以上、個人向けは600名以上に、多様な受講者に講座をしてきました。
「今日は伝わった」「今日は伝わらなかったかもしれない」たくさんの試行錯誤をして分かったこと。
それは、
話し方のうまさやカリスマ性ではなく、“構造化と思いやり”の積み重ね。
この章では、現場で実感した「伝わる講師」に共通する4つのポイントを紹介します。
① 専門知識より“構造化のうまさ”が武器になる
講師として本当に強いのは、専門知識の多さではありません。
むしろ必要なのは、
“情報を順番に並べる力(構造化)”です。
- 結論 → 理由 → 例 → まとめ
- Before → After → How
- 問題 → 解決策 → 実践手順
こうした“型”を自然に使える人の話は、聞き手にストレスを与えません。
逆に、専門知識が豊富でも構造化できない人の話は、
- 話が飛ぶ
- 何が重要かわからない
- 途中で迷子になる
という状態になりがち。
構造さえ整えば、難しい内容も驚くほど伝わる形に変わります。
② 言語化が苦手でも、質問から補えばOK
「講師って言語化が得意じゃないと無理ですよね?」
よくこう言われますが、それは誤解です。
言語化が苦手でも、
“質問”を使えば、いくらでも言語化できるようになります。
たとえば、
- なぜその方法を選んだ?
- どこでつまずいた?
- 何が改善のきっかけになった?
- どの順番で実践した?
こうした質問に答えるだけで、自然と経験が言語化されます。
言語化は才能ではなく、設計で補えるスキルです。
③ 話すより“聞く姿勢”のある講師は愛される
伝わる講師ほど、“話す力”より“聞く力”が強いです。
- 反応を読む
- 相手の表情を察する
- 質問を拾う
- 空気を感じ取る
こうした“聞く姿勢”が、信頼感をつくります。
私が経験した中でも、特に印象的だったのは、
行政の研修で経験した「反応ゼロの3時間」。
その場では誰もリアクションをせず、
「もうこの案件来ないかも…」と思いながら淡々と講座を進めました…。
でも、講座後に職員さん経由で“熱すぎる感想”が届いたのです。
リアクションが見えなくても、
聞く姿勢=“相手を尊重する姿勢”が伝わっていたからだと感じています。
話すのが得意でなくても、
相手を大切にできる講師は必ず選ばれます。
④ “共感→解説→例→まとめ”の型が自然と使える
伝わる講師は、意識していなくても
“共感→解説→例→まとめ”
の流れで話しています。
この型は、講師の話の“わかりやすさ”を決める最重要ポイント。
例:
- 共感
「ここで悩む人が多いんですよ」 - 解説
「理由はこうです」 - 例
「実際に私が関わった企業でも〜」 - まとめ
「つまり、ここを押さえると伝わります」
この流れを守るだけで、
聞き手は迷わず、安心して話を追えます。
第5章:講師を目指す人が最初にやるべきこと
講師として活動を始めたい人は、
「どんな内容を話せばいいのか?」
「台本はどう作ればいいのか?」
と悩むことが多いものです。
でも実は、スタート地点はそこではありません。
講師として最初に整えるべきは“話す内容”ではなく“軸”と“場数”
だということ。
ここでは、初心者が最短で“伝わる講師”に近づく3つのステップを紹介します。
① 自分の「伝えたい一言」を言語化する
台本を作る前に必ずやってほしいのが、
「自分は何を一番伝えたいのか?」という一言を言語化すること。
これは講師としての“芯”になります。
例:
- 「自然体でも伝わる講座は作れる」
- 「行動は設計すれば変えられる」
- 「発信は才能より構造で決まる」
この“軸の一言”があるだけで、
- 台本がぶれなくなる
- 内容を削る基準ができる
- 何度話しても伝わりが安定する
というメリットがあります。
私自身も、講座づくりで“台本は最後、軸は最初”という順番を徹底していました。
この一言が、講師としてのブランドを形づくります。
② 1分自己紹介を作る
講師を目指す人ほど、まず最初に
「1分の自己紹介」 を作るべきです。
理由はシンプルで、
自己紹介には講師の“すべて”が表れるから。
- どんなテーマを扱うのか
- なぜそのテーマなのか
- どんな人に向けて話すのか
- どんな経験を価値として伝えられるのか
1分に凝縮しようとすると、
自然と“講師としての軸”が浮き上がってきます。
私の講座でも、最初にここを固めることで台本の質が一気に変わりました。
プロフィールや肩書きを整える前の「土台」としても機能します。
③ 小さな場で話して感覚をつかむ
講師として一番成長するのは、
実際に人前で話した経験を積んだときです。
これは、私自身の経験が証明しています。
私は最初の講座を、
所属していたコミュニティで“無料開催”し、
参加者からの感想で改善点を得て、
自信と方向性を掴んでいきました。
この最初の“小さな場”があったからこそ、
- 話す順番の調整
- 例え話の強化
- 緊張との向き合い方
- 参加者との距離感づくり
が磨かれ、
その後の行政・大企業の講座にもつながっていきました。
いきなり大舞台を狙う必要はありません。
まずは1人、5人、10人の前で話すところから。
これが、講師としての勘と“伝わる感覚”を育ててくれます。
まとめ|講師に向いているのは“伝えたい想いがある人”
講師に向いているかどうかは、
話し方の上手さや表現力では決まりません。
大切なのは、
「届けたい想いがあるかどうか」
そして
「相手の理解に寄り添えるかどうか」
この2つだけです。
話し方は、練習すれば必ず伸びます。
構造化も言語化も、“才能”ではなく“技術”です。
あなたの経験やストーリーも、発信設計を通じて必ず価値に変わります。
私が見てきた中でも、
本当に伝わる講師は例外なく、
「相手にしっかり届けたい」という姿勢を持っていました。
あなたにも、その想いがあるはず。
その想いさえあれば、
話し方が苦手でも、緊張しても、完璧でなくても大丈夫。
言語化と発信設計で、誰でも“伝わる講師”になれる。
この記事が、あなたの最初の一歩を後押しできたら嬉しいです。